特定技能「外食」2号試験対策に合格するには? 「外食業特定技能2号技能測定試験」 サンプル問題を無料公開!
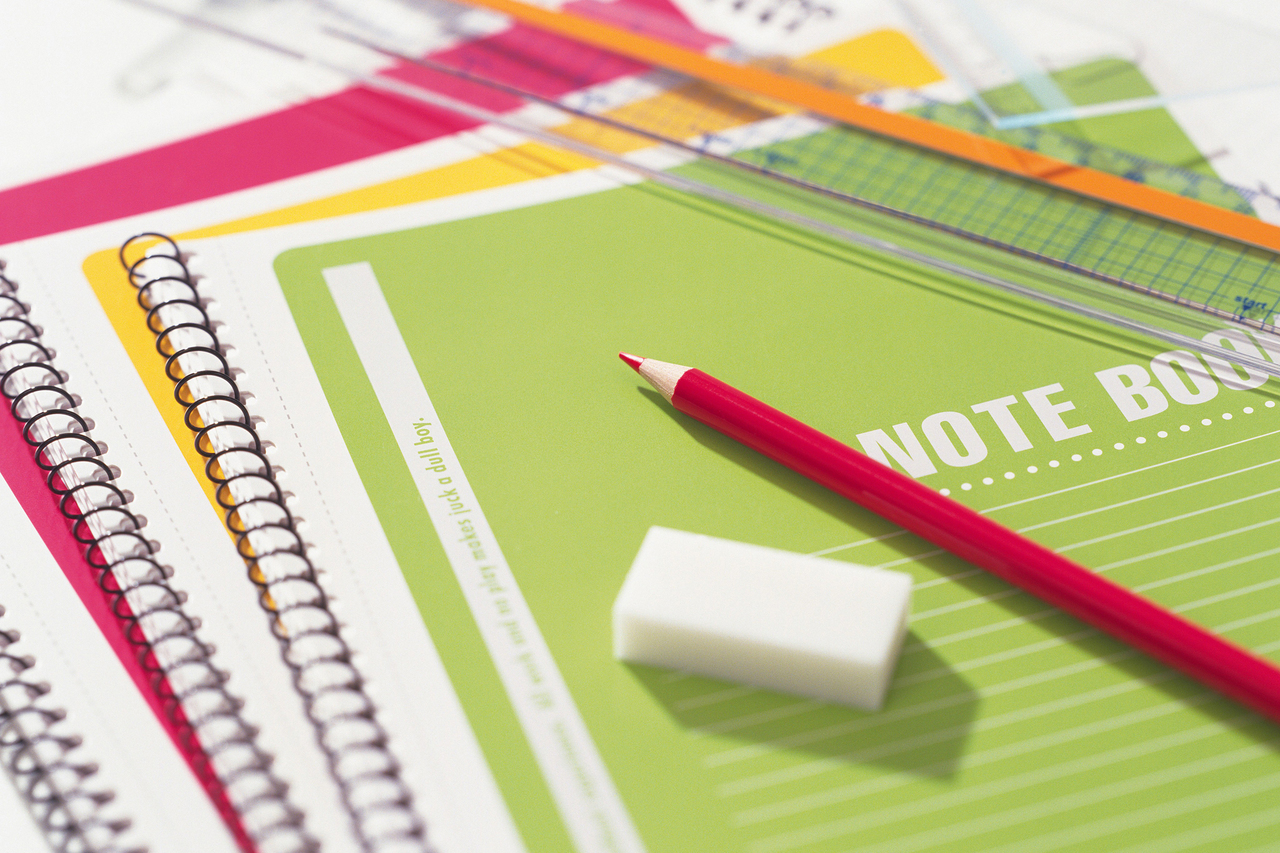
合格のコツと想定問題をお伝えします!
外食業特定技能2号の試験とは?
日本で外食分野の知識や技能を試す試験が実施されています。
この試験は、特定技能外国人の方が個人で申し込むことはできず、現在は雇用している企業を通じて受験申請を行う仕組みになっています。
試験に合格し、特定技能2号を取得すると、お仕事の幅がぐんと広がります。
2号の在留資格は更新の上限がなく、長期にわたって日本で働くことが可能になります。
さらに、ご家族を日本に呼び寄せることもでき、安定して働き続けることで永住権の申請も視野に入れることができます。
スキルアップを目指しながら、より充実したお仕事に取り組み、安心して日本での生活を続けられる ーーそれが特定技能2号の大きな魅力です。
将来の可能性を広げるためにも、ぜひ試験合格を目指してチャレンジしてください。
外食業特定技能2号の試験とは?
受験資格は、次のア~エの全てを満たす人です。
ア. 試験の日に在留資格を有する人
イ. 試験日の時点で満17歳以上である
ウ. パスポートの所持
エ. 試験の前日までに外食業分野において複数のアルバイトや特定技能外国人などを指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、サブリーダーや副店長など店舗管理を補助する実務経験(指導実務経験)を2年以上有する、または試験の前日までに指導実務経験を2年以上有することが見込まれること
※「エ」は先述した実務経験を指します。
合格基準は、満点(250点)のうち65%以上です。
「7割近くも正解しないといけないのか…」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、心配はいりません。
試験には公式の学習テキストが用意されており、一般社団法人 日本フードサービス協会のサイトから取得できます。出題はすべてこのテキストから行われるため、しっかりと学習すれば必ず力になります。
正しい対策を積み重ねれば、合格は十分に目指せます。安心して学習に取り組んでいきましょう。
勉強は大変に感じることもありますが、学ぶ内容は実際のお仕事に直結し、日々の現場で必ず役立ちます。
未来のお仕事のために、そして自分自身のキャリアのために、しっかりと対策を重ねていきましょう。
想定問題65本ノック!(学科試験対策)
想定問題を65本大公開!
実際の試験をイメージしながらチャレンジできる練習問題をまとめました。
ぜひ解いてみて、理解度をチェックしながら自信をつけていきましょう!
【1.衛生管理】★重要★
問題1
食中毒の原因として誤っているものを1つ選びなさい。
1 インフルエンザウイルス
2 サルモネラ菌
3 ノロウイルス
4アニサキス
回答:1
解説: サルモネラ菌は代表的な食中毒菌で鶏卵や食肉などから感染する。
食中毒の90%以上は、細菌やウイルスによって発生します。細菌性食中毒の原因となる物質は腸管出血性大腸菌(O157など) 、サルモネラ属菌、ブドウ球菌などです。ウイルス性食中毒の主な原因物質はノロウイルスやE型肝炎ウイルスなどです。また、科学性食中毒の主な原因物質は洗剤、殺虫剤、農薬です。寄生虫食中毒はアニサキスや回虫が原因となります。
問題2
加熱しても毒素が残り、食中毒の原因となる菌はどれですか。
1 大腸菌O157
2 ボツリヌス菌
3 黄色ブドウ球菌
4 ノロウイルス
回答:3
解説: 黄色ブドウ球菌は食品中で毒素(エンテロトキシン)を作り、加熱しても毒素が残るため注意が必要です。
問題3
生牡蠣などを原因とし、冬季に流行しやすい食中毒の原因はどれですか。
1 ノロウイルス
2 腸炎ビブリオ
3 サルモネラ菌
4 ウェルシュ菌
回答:1
解説: ノロウイルスは冬に多く、二枚貝から感染することが多いです。感染力が強いため集団食中毒につながります。
問題4
腸炎ビブリオの特徴として誤っているものはどれですか。
1 夏に多い
2 潮干狩りや魚介類で感染することが多い
3 真水に弱い
4 加熱に強い
回答:4
解説: 腸炎ビブリオは海水を好む菌で、夏に多発します。魚介類の生食が原因となり、真水に弱いという特徴があります。
問題5
ご飯や弁当などを原因に食中毒を起こす菌はどれですか。
1 ウェルシュ菌
2 セレウス菌
3 ボツリヌス菌
4 腸炎ビブリオ
回答:2
解説: セレウス菌は米飯や麺類などに増殖しやすく、加熱後に放置すると食中毒を引き起こすことがあります。
問題6
カレーやシチューなど、大量調理をして室温で放置すると増える菌はどれですか。
1 腸炎ビブリオ
2 サルモネラ菌
3 ウェルシュ菌
4 黄色ブドウ球菌
回答:3
解説: ウェルシュ菌は酸素が少ない環境で増える「嫌気性菌」で、大鍋料理を室温で放置したときに食中毒を起こしやすいです。
問題7
HACCPの目的として正しいものはどれか。
1 食品を美味しくする
2 食品の安全を確保する
3 調理時間を短くする
4 廃棄を減らす
回答:2
解説: HACCPは危害要因を分析し、重要管理点を設定する食品衛生管理手法。HACCPとは、Hazard Analysis and Critical Control Pointのそれぞれの頭文字をとった略称です。日本語では「危害要因分析重要管理点」と訳されています。
問題8
ノロウイルスの消毒に有効なものはどれか一つ選びなさい。
1 アルコール消毒
2 次亜塩素酸ナトリウム
3 クエン酸水でよく洗う
4 高温多湿に保管
回答:2
解説: ノロウイルスはアルコールに強く、塩素系消毒剤で処理する。
問題9
手洗いが必要なタイミングとして適切でないものはどれか。
1 出勤時
2 トイレの後
3 生肉を扱った後
4 作業内容が2回変わったとき
回答:4
解説: 感染防止のため、調理・接客のあらゆる場面で徹底した手洗いが必要。作業内容変更時の手洗いも大切。
問題10
異物混入防止として適切な対応はどれか。
1 帽子やマスクを着用する
2 指輪をしたまま調理する
3 爪を長く保つ
4 私物を調理場に置く
回答:1
解説: 頭髪や唾液からの異物混入を防ぐため、帽子やマスクを使う。
問題11
食品の温度管理で「チルド」と呼ばれるのは何度程度か。
1 −10℃以下
2 0〜5℃
3 5〜10℃
4 15~20℃
回答:2
解説: チルドは0〜5℃で細菌の増殖を抑える温度帯。
問題12
調理済み食品は室温で何時間以内に食べるべきか。
1 1時間
2 2時間
3 5時間
4 10時間
回答:2
解説: 食中毒菌の繁殖を防ぐため、室温放置は2時間以内が目安。
問題13
食中毒予防の3原則はどれか。
1 清潔・加熱・冷却
2 つけない・増やさない・やっつける
3 早い・安い・美味しい
4 乾燥・保存・凍結
回答:2
解説: 「つけない」「増やさない」「やっつける」が予防の基本。
問題14
冷凍食品を解凍する方法として適切なのはどれか。
1 室温で放置
2 冷蔵庫で解凍
3 太陽光に当てる
4 常温の水に放置
回答:2
解説: 冷蔵庫内でゆっくり解凍するのが安全。
問題15
消毒用アルコールの濃度として適切なのはどれか。
1 10%
2 40%
3 70%
4 99%
回答:3
解説: 70%前後が最も殺菌効果が高い。
問題16
食器洗浄で最も重要な点はどれか。
1 見た目がきれいかどうか
2 洗剤を大量に使う
3 十分にすすぎ、乾燥させる
4 短時間で終わらせる
回答:3
解説: 残留洗剤や菌の繁殖を防ぐため、十分にすすいで乾燥させる。
問題17
食中毒菌が最も繁殖しやすい温度帯はどれか。
1 −10〜0℃
2 0〜5℃
3 10〜60℃
4 70℃以上
回答:3
解説: 10〜60℃は「危険温度帯」と呼ばれる。
問題18
調理従事者が感染症にかかった場合、どうすべきか。
1 発熱がない場合は働く
2 上司に報告して従事を控える
3 手袋をしてこまめに手洗いをして働く
4 マスクをして働く
回答:2
解説: 食品衛生を守るため、症状がある場合は報告し従事しない。
問題19
衛生管理で「ゾーニング」とは何を意味するか。
1 調理器具の名前
2 作業区域を区分けすること
3 店舗の装飾方法
4 従業員のシフト表
回答:2
解説: 清潔区域と不潔区域を分け、交差汚染を防ぐ。
問題20
廃棄物管理で適切な対応はどれか。
1 廃棄物は長時間置いてからまとめる
2 こまめに廃棄し、密閉容器で管理する
3 開放容器に入れておく
4 廃棄物は冷蔵庫に入れる
回答:2
解説: 廃棄物は害虫や臭気の発生源になるため、密閉管理が必要。
【2.飲食物調理】
問題21
日本料理でだしを取るときに主に使われる材料はどれか。
1 鶏肉と卵
2 昆布と鰹節
3 米のとぎ汁と麦
4 野菜と果物
回答:2
解説: 日本料理では昆布と鰹節が代表的なだしの材料。
問題22
米を炊く前に行う「研ぐ」作業の目的はどれか。
1 米の色を白くする
2 表面の糠を落とす
3 米粒を割る
4 炊飯時間を短くする
回答:2
解説: 糠臭さを取り除き、風味をよくするために研ぐ。
問題23
肉を加熱する主な目的はどれか。
1 色を変化させて見た目をよくするため
2 食中毒菌を死滅させるため
3 柔らかくして食感をよくするため
4 風味を良くするため
回答:2
解説: 加熱の第一目的は食品の安全確保。
問題24
野菜の下茹での目的として正しいものはどれか。
1 栄養を閉じ込める
2 アクや臭みを除く
3 水分量を増やす
4 色を黒くする
回答:2
解説: 下茹ではアク抜きや色止めのために行う。
問題25
冷蔵庫で保存すべき食品はとして誤っているものはどれか。
1 果物
2 缶詰
3 生肉
4 卵
回答:3
解説: 特に生肉は腐敗しやすいため冷蔵保存が必須。缶詰は冷蔵保存不要。
問題26
魚の三枚おろしとは何か。
1 頭と尾を落とすこと
2 骨ごと輪切りにすること
3 骨を中心に身を左右に分けること
4 皮をすべて取ること
回答:3
解説: 三枚おろしは背骨を中心に左右に分ける調理法。
問題27
野菜のビタミンCをできるだけ失わない調理法はどれか。
1 低温でゆでる
2 蒸す
3 高温で揚げる
4 直火で焼く
回答:2
解説: 蒸すと水に溶けやすいビタミンCの流出を防げる。
問題28
食品表示法で義務付けられているアレルゲン表示の対象に含まれるものはどれか。
1 米
2 牛乳
3 落花生
4 かに
回答:1
解説: 特定原材料7品目(卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに)が義務表示対象。
問題29
調味料の「さしすせそ」の正しい順序はどれか。
1 さ=酒、し=塩、す=砂糖、せ=醤油、そ=味噌
2 さ=砂糖、し=塩、す=酢、せ=醤油、そ=味噌
3 さ=砂糖、し=酢、す=塩、せ=味噌、そ=醤油
4 さ=塩、し=砂糖、す=酢、せ=醤油、そ=味噌
回答:2
解説: 砂糖→塩→酢→醤油→味噌の順に入れると味が染み込みやすい。
問題30
「五味」に含まれないものはどれか。
1 甘味
2 酸味
3 渋味
4 苦味
回答:3
解説: 五味は甘味・塩味・酸味・苦味・うま味。渋味は含まれない。
問題31
天ぷらをカラッと揚げるために適した油の温度はどれか。
1 100℃前後
2 140℃前後
3 170〜180℃
4 200℃以上
回答:3
解説: 衣がカラッと仕上がるのは170〜180℃。
問題32
野菜を切った後に水にさらす主な目的はどれか。
1 栄養が逃げないようにする
2 アクを抜く
3 甘みを強める
4 腐敗を防ぐ
回答:2
解説: 水にさらすことでアクやえぐみを取り除く。
問題33
日本酒を料理に加える効果として正しいものはどれか。
1 甘味を加える
2 臭みを消す
3 食中毒を防ぐ
4 食中毒の原因となる菌を死滅させる
回答:2
解説: 日本酒のアルコール成分や香りで魚や肉の臭みを和らげる。
問題34
「漬物」について誤っているものはどれか。
1 栄養が増える
2 微生物の働きで風味を増す
3 保存性が高い
4 発酵が原因で腐敗を早める
回答:4
解説: 乳酸菌発酵などで保存性が高まり、栄養や風味も増す。
問題35
「だし昆布」を煮出すときに適切な温度はどれか。
1 100℃
2 50〜60℃
3 冷水
4 120℃以上
回答:2
解説: 昆布の旨味成分グルタミン酸は60℃前後で溶け出す。
問題36
刺身を切るときに使うときに最も適した包丁はどれか。
1 柳刃包丁
2 出刃包丁
3 薄刃包丁
4 三徳包丁
回答:1
解説:
柳刃包丁:刃渡りが長く、主に刺身を切るときに使用する包丁で「刺身包丁」とも呼びます。
出刃包丁:魚をさばくときに使用する包丁です。重みがあり、刃に厚みもあるため、骨を切ったりすることもできます。
菜切包丁:日本の和包丁で、野菜を切ることに適しています。三徳包丁に比べ、野菜のみじん切 せん ぎ りや千切りなどがしやすいです。
薄刃包丁:菜切包丁と同じく日本の和包丁で、野菜を切ることに適しています。野菜の皮むきや、 きざ てき 刻むのに適しています。
牛刀:もともとは肉専用包丁として設定されましたが、肉以外にも魚や野菜などを切ることにも使用できます。
三徳包丁:肉、魚、野菜など様々な食材に使用できる包丁です。
ペティナイフ:小型の包丁。野菜や果物の皮むきなど細かい作業をするのに便利です。
中華包丁:中華料理を作る際に使用する包丁です。刃の重みで肉や魚、野菜を切ったり、刃の平面で食材をつぶすことなどもおこなうことができます。
問題37
肉の「筋切り」を行う目的はどれか。
1 旨味を逃がすため
2 硬さを防ぐため
3 色を変えるため
4 焼き色をつけるため
回答:2
解説: 筋を切ることで加熱時の収縮を防ぎ、柔らかく仕上がる。
問題38
冷凍保存する際に避けるべき状態はどれか。
1 急速冷凍
2 小分け保存
3 再冷凍
4 ラップに包む
回答:3
解説: 再冷凍は品質劣化や食中毒のリスクを高める。
問題39
炒め物を行う際に適した鍋の温度はどれか。
1 90℃
2 160〜170℃
3 200℃以上
4 80℃程度
回答:2
解説: 160〜170℃の中温で加熱すると焦げすぎず旨味が引き出される。
問題40
調理における「下味」をつける目的はどれか。
1 見た目を良くする
2 栄養を増やす
3 風味や味をつける、調理後の味なじみを良くする
4 保存期間を長くする
回答:3
解説: 下味は食材の風味を引き立て、味付けを均一にする。
【3.接客全般】
問題41
接客の基本姿勢で最も重要なのはどれか。
1 お客様を観察する
2 お客様に笑顔で対応する
3 お客様に指図する
4 お客様を避ける
回答:2
解説: 第一印象を良くし、安心感を与えるのは笑顔。
問題42
クレーム対応で最も重要なのはどれか。
1 すぐに起こってしまったことの理由を説明する
2 謝罪と迅速な対応
3 上司が対応できるまで待ってもらう
4 お客様を店外へ案内する
回答:2
解説: まず謝罪し、解決に向け迅速に対応する。クレームの対応は①丁寧に謝る→②お客様の言い分を聞く→③迅速な処理→④責任者への報告と責任者の対応→⑤クレーム処理報告書や日報で本部へ報告、これが基本です。1号試験のテキストでも、もう一度復習しておきましょう。
問題43
接客で「報・連・相」が意味するものはどれか。
1 報酬・連絡・相談
2 報告・連絡・相談
3 報復・連携・総会
4 報知・連絡・相槌
回答:2
解説: 職場内の円滑な情報共有の基本。
問題44
外国人のお客様に接客する際、最も重要な点はどれか。
1 完璧な発音で話す
2 ゆっくり、簡単な言葉で伝える
3 声を大きくする
4 翻訳アプリに頼る
回答:2
解説: わかりやすい言葉で伝えることが大切。
問題45
満席時の対応で適切なのはどれか。
1 無理にでも席を詰める
2 丁寧に待ち時間を伝える
3 お客様を刺激しないよう、何も言わない
4 入店を断る
回答:2
解説: 待ち時間を明確に伝えることで安心感を与える。
問題46
高齢者のお客様に飲み物を提供する際の配慮はどれか。
1 熱すぎない温度にする
2 大きな声で叱る
3 ストローを使わない
4 何も配慮しない
回答:1
解説: 高齢者はやけどしやすいため、温度に注意が必要。
問題47
サービスの流れとして正しいものはどれか
1 案内→水・おしぼり・メニューの提供→注文受け→料理提供→中間下げ→デザート・ドリンクの提供→レジ精算→下げ
2 案内→水・おしぼり・メニューの提供→注文受け→料理提供→デザート・ドリンクの提供→中間下げ→レジ精算→下げ
4 案内→メニューの提供→注文受け→水・おしぼり→料理提供→中間下げ→デザート・ドリンクの提供→下げ→レジ精算→レジ精算
回答:1
基本のサービスの流れは「案内→水・おしぼり・メニューの提供→注文受け→料理提供→中間下げ→デザート・ドリンクの提供→レジ精算→下げ」
問題48
料理を提供するときに適切な言葉はどれか。
1 「はい、これです」
2 「お待たせいたしました」
3 「恐れ入ります」
4 「お粗末様でした」
回答:2
解説: 丁寧な表現が信頼を生む。
問題49
お客様からの注文を復唱する目的はどれか。
1 時間稼ぎのため
2 正確に注文を確認するため
3 お客様を困らせるため
4 注文を断るため
回答:2
解説: 復唱で間違いを防ぎ、安心感を与える。
問題50
食後に使う挨拶で適切なのはどれか。
1 「ありがとうございました」
2 「いらっしゃいませ」
3 「どういたしまして」
4 「ごゆっくりどうぞ」
回答:1
解説: 感謝の気持ちを伝える言葉が基本。
問題51
子連れのお客様に配慮すべき点はどれか。
1 子どもに熱い料理を置かない
2 通路をふさぐ席に案内する
3 子どもにも大人用の食器を渡す
4 子供も平等に大人と同じように接する
回答:1
解説: 安全に配慮することで安心して食事できる。
問題52
接客中に知らない質問をされた場合の正しい対応はどれか。
1 わかるところだけを答える
2 「わかりません」と正直に伝え調べる
3 わかる人が来るまで待たせておく
4 間違っていてもいいので早く答える
回答:2
解説: 正確さと誠実さが信頼を築く。
問題53
お客様を呼ぶときに適切なのはどれか。
1 「お客!」
2 「お客様」
3 「貴方様」
4 「ご主人様」
回答:2
解説: 敬意を持って呼びかける。
問題54
会計時に必要な配慮はどれか。
1 金額を大声で読み上げる
2 金銭を丁寧に扱う
3 落とさないように強い力で釣り銭を渡す
4 安心していただくためにお客様に計算を任せる
回答:2
解説: 金銭を丁寧に扱うことがお客様への礼儀。
問題55
接客における「ホスピタリティ」とは何を意味するか。
1 経済性
2 おもてなしの心
3 速さ
4 利益優先
回答:2
解説: お客様を思いやる気持ちがホスピタリティ。
問題56
調理場以外の清掃をする際の使用道具について誤っているものをひとつ選びなさい。
1 ショーケースや鏡をフィトルモップで拭く
2 玄関の床を薄めた洗剤でモップがけをする
3 窓ガラスをボアダスターで拭く
4 大型窓の掃除にはスクイージーを使用する
回答:1
解説:フィトルモップは床掃除に使用する。掃除マニュアルも確認しておきましょう。
【4.店舗運営】
問題57
飲食店の開店前に必ず行うべき作業はどれか。
1 清掃・点検・仕込み
2 会計処理
3 広告作成だけ
4 閉店作業
回答:1
解説: 安全で円滑な営業のため、開店準備は必須。
問題58
在庫管理の目的として最も適切なのはどれか。
1 廃棄を増やすため
2 食材のロスを減らすため
3 品切れを放置するため
4 倉庫を散らかすため
回答:2
解説: 適切な在庫管理でコスト削減と品質維持が可能。
問題59
売上の管理に用いられる書類はどれか。
1 伝票・レジ記録
2 新聞
3 チラシ
4 電話帳
回答:1
解説: 売上管理には伝票やレジ記録が基本資料となる。
問題60
飲食店で「FLコスト」と呼ばれるのは何か。
1 食材費と人件費
2 光熱費と家賃
3 広告費と雑費
4 融資と借金
回答:1
解説: FoodとLaborの合計。飲食店経営の重要指標。
問題61
従業員教育で重視すべきことはどれか。
1 マニュアルと実践両方の指導
2 放任主義
3 厳罰のみ
4 全く教育しない
回答:1
解説: マニュアルと実務経験を組み合わせるのが効果的。
問題62
シフト管理で最も重視すべき点はどれか。
1 偏りなく人員を配置する
2 同じ人ばかりに依頼する
3 深く考えずに作る
4 全員休みにする
回答:1
解説: 安定した運営には公平で計画的なシフトが不可欠。
問題63
店舗の原価率を下げる方法として適切なのはどれか。
1 廃棄を減らす
2 値引きを増やす
3 不要なものも仕入れる
4 高級食材を多めに使う
回答:1
解説: 廃棄を減らせば食材の有効利用につながる。
問題64
飲食店の立地選びで重要な要素はどれか。
1 人通りや交通の利便性
2 周囲に何もない場所
3 車が入れない場所
4 情報が届かない場所
回答:1
解説: 集客には人通りの多さやアクセスの良さが大きく影響。
問題65
POSシステムの主な役割はどれか。
1 天気を予測する
2 売上や在庫を管理する
3 調理をする
4 音楽を流す
回答:2
解説: POSは販売時点情報管理で、売上・在庫のデータ化に有効。
問題66
飲食店における「利益」とは何か。
1 売上から経費を引いた残り
2 売上の総額
3 売り上げから借金額を引いた残り
4 廃棄物の処理費用
回答:1
解説: 利益は売上高から仕入・人件費・光熱費などの経費を差し引いたもの。
【基本用語確認】
【問題67】
「アイドルタイム」の意味として正しいものはどれか
1 お客様からオーダーを承り、料理提供されるまでの時間のこと
2 お客様が集中して来店される時間帯のこと。
3 客数の少ない時間帯
4 利用客が一定期間に何回来店するかを表すことば
回答:3
解説:
アイドルタイム: 客数の少ない時間帯を意味し、ピークタイムとは反対の言葉。外食産業では食事時間がピークとなるため、その合間はアイドルタイムとなる。この時間帯は人件費を削減し、サイドワークや教育トレーニングを実施する。
ピークタイム:お客様が集中して来店される時間帯のこと。従って、売上計画を基にこの時間帯を中心にワークスケジュールを組み、仕込み作業や点検補充作業、清掃作業などはピークタイム前に 完了し、お客様を迎える必要がある。
1はサービングタイム: お客様からオーダーを承り、料理提供され るまでの時間のこと。通常、ファミリーレストランではランチタイム5分~7分、ディナー12分~15分がその目安。売上予測に基づく、適正 な仕込み量と準備作業の徹底が決め手。
4は来店頻度: 利用客が一定期間に何回来店するかを表す。通常、客単価が高い業態は来店頻度が低く、商圏を広く設定する必要がある。また、客単価が低い業態は来店頻度が高くなり、商圏が 狭くても経営が成り立つことが多い。
【問題68】
OJT に対し本部などで知識や理念を理解させるために実施する集合教育をなんというか。
1 OffJT
2 QSC
3 トレーニング プログラム
4 人事考課
回答:1
解説: 現場(店舗)での作業技術を体得するために じっ し 実施されるトレーニングのことをOJTといいます。 On the Job Training の略称。OJTは原則としてトレーナーとト レーニー(教わる側)とのマンツーマン(1人 対1人)で訓練する。
OffJTはOJT に対し本部などで知識や理念を理解させるために実施する集合教育をいいます。Off the Job Trainingを略したものです。教育訓練のポイントはこの二つをバランスよく組みトレーニングプ ログラムを作成することである。
QSCはトレーニング プログラム] Q(Quality=商 品 の 品 質)、S(Service= せいけつ サービス)、C(Cleanliness=清潔)のことで、 店舗オペレーションをとおしてお客様に心から 満足を与えるために必要な、外食ビジネス成功最も重要な3要素。
トレーニング プログラムとは店舗オペレーションに必要な作業技術の習得や、社員のマネジメント能力を短期間で育成するための教育訓練プログラムのこと。教育訓 練はマニュアルやビデオ、チェックリストなどのツールにより店や本部で実施される。
外食特定技能2号試験には実技試験もあります
実技試験は大きく2つの形式で構成されています。
ひとつは、図やイラストを見て正しい行動を判断できるかを確認する 「判断試験」。
もうひとつは、計算式を使って作業の計画を立てられるかを測る 「計画立案」 です。
ここでは、その実技試験を想定したサンプル問題をご用意しました。
本番さながらの雰囲気をイメージしながら、ぜひチャレンジしてみてください!
実技想定問題 5題!
問題1(実技想定)
次のイラストに示された包丁の持ち方で正しいものはどれか。
(イラスト:握り方の図が提示される)
1 柄を全て握りこむ
2 人差し指をそえて軽く握る
3 刃を直接持つ
4 逆手で持つ
回答:2
解説: 包丁は柄を握り、人差し指を添える「正しい握り方」が安全。
問題2(実技想定)
次の図に示す「きゅうりの切り方」のうち、小口切りを示しているのはどれか。
(図:輪切り・斜め切り・乱切り・せん切りのイラスト)
1 輪切り
2 乱切り
3 せん切り
4 半月切り
回答:1
解説: 小口切りは細長い野菜を端から輪切りにしていく切り方。
問題3(実技想定)
盛り付け図を見て、正しい和食の配膳位置を選びなさい。
(図:左にご飯、右に汁物、奥に主菜、副菜が並んでいる配置図)
1 ご飯は右、汁は左
2 ご飯は左、汁は右
3 ご飯と汁を逆に置く
4 ご飯は真ん中
回答:2
解説: 日本の基本配膳は「一汁三菜」で、ご飯は左、汁は右。
問題4(実技想定)
下の温度計の図を見て、中心温度が正しく計測できているか判断せよ。
(図:肉の中心に温度計が刺さっている/表面だけに刺している例あり)
1 中心部に刺さっているので正しい
2 表面だけに刺しているので誤り
3 空気中に刺しているので誤り
4 鍋底に当てているので誤り
回答:1
解説: 食中毒防止のため、肉や魚は「中心温度75℃・1分以上」が基準。
問題5(実技想定)
次のイラストに示された手洗い手順のうち、抜けている部分はどこか。
(図:手のひら→手の甲→指の間→親指→爪先→手首の図解)
1 手のひら
2 指の間
3 親指
4 手首
回答:3
解説: 親指周りは汚れが残りやすく、手洗いで忘れやすい部分。
いかがでしたでしょうか?
想定問題でイメージをつかみ、テキスト学習で知識を深めれば、きっと本番も大丈夫です。
一歩ずつ準備を重ねて、自信を持って試験に挑んでください。
私たちは、あなたの合格と新しい未来を心から応援しています!
計算問題にもチャレンジ!
外食2号試験には計算問題も出題されます。
大問と小問の構成となることが多い傾向です。
チャレンジ問題を公開しますので、テキストを確認して挑戦してみてください。
●大問1 原価率と荒利益率の計算
ハンバーグ定食の販売価格は 800円。
原材料費は以下の通りです。
| 材料 | 単価 | 使用量 | 原価 |
|---|---|---|---|
| ハンバーグパテ | 120円/個 | 1個 | 120円 |
| ソース | 80円/100cc | 50cc | 40円 |
| 添え野菜 | 40円/セット | 1セット | 40円 |
(1) この商品の原価合計はいくらですか。
(2) (1)の結果を使って、原価率を求めてください。
(計算式:原価 ÷ 売価 × 100)
(3) 荒利益率と荒利益額を求めてください。
(ヒント:荒利益率 = 100%-原価率)
ーーーーー
【回答&解説】
前提:売価800円/原価=120+40+40
(1) 原価合計
答:200円
解説:120+40+40=200円。
(2) 原価率
答:25.0%
解説:200÷800×100=25.0%。
(3) 荒利益率・荒利益額
答:荒利益率 75.0%、荒利益額 600円
解説:荒利益率=100-25=75%。荒利益額=800-200=600円。
●大問2 実際原価率とロスの計算
ある月の売上高は 20,000円、
前月末棚卸し額が 2,000円、当月仕入額が 8,000円、当月末棚卸し額が 3,000円 でした。
(1) 当月実際原価を求めてください。
(計算式:(前月末棚卸+当月仕入)-当月末棚卸)
(2) (1)の結果を使い、当月実際原価率を求めてください。
(計算式:実際原価 ÷ 売上高 × 100)
(3) 標準原価率が 40% の場合、ロス率を求めてください。
(計算式:実際原価率-標準原価率)
ーーーーー
【回答と解説】
実際原価率とロスの計算
前提:売上高20,000円/前月末2,000円・仕入8,000円・当月末3,000円/標準原価率40%
(1) 当月実際原価
答:7,000円
解説:(2,000+8,000)-3,000=7,000円。
(2) 当月実際原価率
答:35.0%
解説:7,000÷20,000×100=35.0%。
(3) ロス率
答:-5.0%(逆ざや5.0ポイント)
解説:実際35.0%-標準40.0%=-5.0%。マイナスは標準より良好=逆ざや。
●大問3 人時売上高と労働分配率の計算
ある店舗の月間売上高は 1,200,000円。
この月の実働時間合計は 300時間、人件費は 360,000円 でした。
(1) 人時売上高(1時間あたりの売上高)を求めてください。
(計算式:売上高 ÷ 実働時間)
(2) 荒利益率を 70% とした場合、荒利益額を求めてください。
(3) (2)を使って、労働分配率を求めてください。
(計算式:人件費 ÷ 荒利益 × 100)大問3 人時売上高と労働分配率の計算
ーーーーー
【回答と解説】
前提:売上高1,200,000円/実働時間300h/人件費360,000円/荒利益率70%
(1) 人時売上高
答:4,000円/時
解説:1,200,000÷300=4,000。
(2) 荒利益額
答:840,000円
解説:1,200,000×0.70=840,000円。
(3) 労働分配率
答:42.9%(小数第1位四捨五入)
解説:360,000÷840,000×100=42.857…% ≒ 42.9%。
※参考:一般に適正範囲は35~40%とされ、今回はやや高め。
いかがでしたでしょうか?
想定問題でイメージをつかみ、テキスト学習で知識を深めれば、きっと本番も大丈夫です。
一歩ずつ準備を重ねて、自信を持って試験に挑んでください。
私たちは、あなたの合格と新しい未来を心から応援しています!



